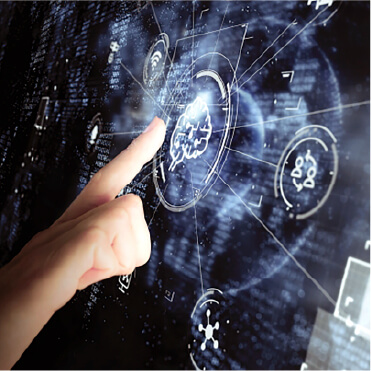もう間違えない!AIの回答が事実かどうかをセルフチェックさせる「ファクトチェックプロンプト」

AI執事「トゥエ」と学ぶ!中小企業のためのやさしい生成AI活用術
ChatGPTはとても便利ですが、時々「これ本当……?」と不安になることはありませんか?
実はAIは“もっともらしい誤情報”を返してしまうことがあるのです。
でも大丈夫。AI自身に“セルフチェック”させれば、信頼性をぐっと高められます。
この記事では、今日から使える簡単な「ファクトチェックプロンプト」をご紹介します。
目次
キャラクター紹介

生成AI執事トゥエ
生成AI執事

まりの
伝統ある洋菓子店で働く広報・PR
AIの答え、全部が本当とは限らない?

まりの
最近、ChatGPTを使って記事や資料を作るようになったんですが……
たまに“あれ?これ本当?”って思うことがあるんです。
AIって間違えることもあるんですよね?

生成AI執事トゥエ
はい、実はその通りです。
AIはとても優秀な助手ですが、“それらしい答え”を作るのが得意なんです。
つまり、正しそうに見えても根拠がないことを言う場合がある。
これを『ハルシネーション(幻覚)』と呼びます。

まりの
なるほど…。でも、AIが間違えるかもしれないなら、どうしたら安心して使えますか?

生成AI執事トゥエ
簡単です。
AI自身に“チェック役”をお願いするプロンプトを追加するだけで、かなり信頼性を高められますよ。

まりの
“AIにチェックさせる”って、どういうことですか?

生成AI執事トゥエ
ChatGPTは、与えられた指示に従って“もう一度考え直す”ことができます。
つまり、回答を出したあとにこう言えばいいのです。
AI執事が教える!ChatGPTの「ファクトチェックプロンプト」とは?
ファクトチェック用プロンプト①
上記の回答について、情報源を明示してください。

生成AI執事トゥエ
この一言で、ChatGPTは自分の回答に使った情報や根拠を説明しようとします。
- 使用例
Q:ChatGPT、スイーツ業界の2024年トレンドを教えて。
A:(トレンドについて回答)
👇 ここでさらに
「上記の回答について、情報源を明示してください。」
- 効果
ChatGPTが「一般的な傾向として」「〇〇のデータに基づいて」など、出典を補足してくれます。
根拠が曖昧な場合も、「確実な情報ではありません」と教えてくれることがあります。
ファクトチェック用プロンプト②
この情報は正確ですか? 根拠を示してもう一度説明してください。

まりの
“正確ですか?”って聞くだけでいいんですか?

生成AI執事トゥエ
はい。ただ“根拠も一緒に”と伝えるのがポイントです。
AIが自分の回答をもう一度検証し、事実に基づく部分と推測を分けて説明してくれます。
- 使用例
Q:ChatGPT、横浜で人気のスイーツ店を3つ教えて。
A:(店名を回答)
👇
「この情報は正確ですか? 根拠を示してもう一度説明してください。」
- 効果
ChatGPTが「これは公式サイトに掲載されています」「これは口コミ情報の傾向です」など、“どの部分が確実で、どこがAIの推測なのか”を明確にしてくれます。
ファクトチェック用プロンプト③
上記の回答に誤りがある可能性を指摘してください。

まりの
えっ、自分の間違いを指摘させるんですか?

生成AI執事トゥエ
はい。AIは“確認モード”になると、驚くほど冷静に自己検証します。
自分で“もしかすると間違っている点”を挙げてくれるんです。
- 使用例
「上記の回答に誤りや曖昧な部分がある場合、それを指摘してください。」
- 効果
ChatGPTが「データの更新時期が古い可能性があります」「この統計は国ごとに差があります」など、不確実な箇所をきちんと教えてくれます。
信頼できるAI活用の3ステップ

まりの
なるほど、チェック用プロンプトを足すだけでいいんですね。
でも、毎回どうやって使い分けたらいいんでしょう?

生成AI執事トゥエ
シンプルに、この3ステップを覚えておくといいですよ。
1️⃣ まず質問する。
(例:「2025年のスイーツ業界の動向を教えて」)
2️⃣ 回答を読んだあと、すぐに“ファクトチェックプロンプト”を追加。
(例:「この情報は正確ですか? 根拠を示してください。」)
3️⃣ 回答を比較し、信頼できる部分だけ採用する。

まりの
つまり、“AIの答えを鵜呑みにしない”ってことですね。

生成AI執事トゥエ
その通りです。
ChatGPTはあなたの“考えるパートナー”であって、“絶対の正解”を出す先生ではありません。
まとめ:AIを“チェック役”として使う時代へ

まりの
ChatGPTって、“答えるだけのAI”じゃなくて、“確認するAI”にもなるんですね。

生成AI執事トゥエ
ええ。特にビジネス文書や記事制作、調査資料などでは、
『AIにもう一度、自分の答えをチェックさせる』ことが重要です。
これを習慣にすれば、誤情報を減らせるだけでなく、あなたの発信の信頼性も上がります。
この記事は2025年11月公開の記事です。技術の進化等により一部内容が異なることもございます。